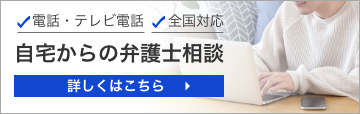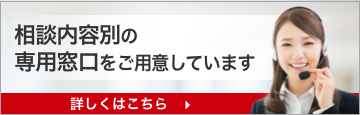手形の不渡りを出すと会社や経営者の生活はどうなるの? 弁護士が解説
- 事業再生・倒産
- 不渡り
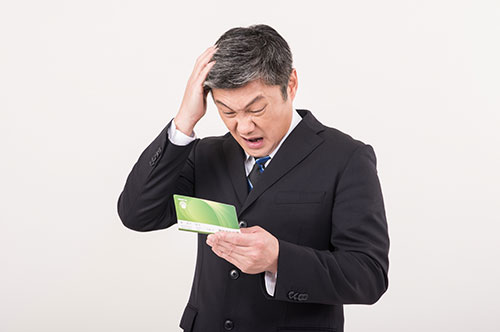
商品の仕入れに必要な資金が不足している場合などは、手形を振り出す方法が便利です。しかし、支払いの期日になって当座預金の残高が不足していると、手形が不渡りになってしまいます。残高の不足で手形が不渡りになると、信用の低下や取引停止などが発生し、最悪の場合は会社の倒産につながる可能性があります。
会社が倒産すると破産手続などを検討することになりますが、水戸地方裁判所では令和2年の破産の新受件数が1322件でした。少なくない数の破産手続が行われていることがうかがえます。手形の不渡りは会社の倒産や破産につながりかねないため、制度をきちんと把握しておくことが大切です。
そこで今回は、手形が不渡りになった場合に会社や経営者にどのような影響が生じるかについて、弁護士が解説します。
1、手形の不渡りとは
手形の不渡りの種類と、不渡りによってどのような影響があるかを解説します。
-
(1)手形の不渡りは3種類ある
手形の不渡りとは、手形を指定の期日に現金化できないことです。手形の不渡りは、不渡りが生じた理由によって3種類に分かれます。
● 0号不渡り
0号不渡りとは、手形を振り出すための形式に不備がある場合や、手形を現金化できる呈示期間以外に現金化しようとした場合などに生じる不渡りのことです。0号不渡りは手形を発行した振出人に責任がないため、取引停止などの処分の対象にはなりません。
● 1号不渡り
1号不渡りとは、手形を振り出した振出人の信用に関係して不渡りが生じることです。振出人の当座預金の残高不足で受取人が手形を現金化できない場合が典型例です。当座預金を解約するなど、振出人と支払銀行の間に取引がない場合も、1号不渡りが生じます。
● 2号不渡り
2号不渡りとは、0号不渡りと1号不渡りにあたらない原因による不渡りのことです。手形を盗まれたり偽造されたりした場合や、手形の振り出しの原因となった契約が債務不履行になった場合などに2号不渡りが生じます。 -
(2)1号不渡りによる影響
手形の不渡りとは、一般に1号不渡りが生じることを意味します。振出人が振り出した手形の受取人が、指定の期日に手形を現金化しようとしたところ、振出人の当座預金の残高が不足していて現金化できなかったなどです。
1号不渡りが発生すると、金融機関は不渡届を手形交換所に提出します。手形交換所とは、その地域の手形や小切手の決済交換を行う場所です。
手形交換所は、その内容を不渡報告に記載して、手形交換所の加盟銀行に通知します。1回目の不渡りの効果はこれで終了です。
「不渡りを出すと倒産」と言われることがありますが、1回目の不渡りだけでは銀行との取引は停止されず、会社は倒産にはなりません。
もっとも、不渡手形を出したことは不渡報告によって周知されるため、資金調達が困難になったり、手形の割引が拒否されたりする可能性があります。1回目の不渡りだけでも、実質的な不利益が生じうるので注意しましょう。
なお、2号不渡りが生じた場合も金融機関が不渡届を作成しますが、2号不渡りは振出人が異議申し立てできます。これに対し、1号不渡りは異議申し立てができませんので、当座預金の残高には十分に注意しましょう。
2、2回の不渡りで、銀行取引停止処分に
問題は、2回目の不渡りを出した場合です。1回目の不渡りから6か月以内に2回目の不渡りを出してしまうと、手形交換所から銀行取引停止処分を受けることになります。
銀行取引停止処分を受けると、手形交換所に参加している金融機関との間で、処分を受けた日から2年間、当座預金と貸し出しの取引ができなくなります。つまり、手形や小切手の振り出しや、新規の融資を受けられなくなってしまうのです。
処分を受けた後も、普通預金口座の利用や現金での取引は可能ですが、不渡りを出すのは一般に経営状態がかなり悪化しているからであり、現金だけで十分な資金繰りをするのは非常に困難です。
また、銀行取引停止処分のうわさが広まれば、金融機関や取引先からの信用を失い、融資や取引を打ち切られてしまう場合が少なくありません。
銀行取引停止処分によって即座に倒産はしませんが、取引停止に伴う資金繰りの悪化や信用の低下などによって、倒産せざるを得ない状況になる可能性が高いということです。
手形の振り出しは支払いの先延ばしなどに便利ですが、不渡りを出すと会社の倒産につながる大きなリスクがあります。金額や振出日に注意を払い、できるだけ安全に運用することが重要です。
3、倒産後の法人についての手続き
法的には倒産の厳密な定義はありませんが、一般に会社の経営がどうにもならなくなった状態を意味します。手形の不渡りによって事実上の倒産になった場合、法人破産の手続きをして債務関係を整理するのが一般的です。
-
(1)法人破産とは
法人破産とは、会社などの法人が破産の手続きをすることです。会社が破産する場合を特に会社破産と呼ぶこともあります。
手形の不渡りで取引停止になるなど、債務超過や支払い不能を解決できなくなった場合には、法人破産を検討します。法人破産によって会社が有する資産と負債を整理し、手持ちの資産で可能な限り負債を支払います。 -
(2)法人破産の効果
法人破産をすると、以下のような効果が生じます。
● 会社が消滅する
法人破産をした法人は消滅し、存在しなくなります。個人が破産する方法として自己破産がありますが、自己破産をしても個人は存続するのに対し、法人破産をした法人は存続せずに消滅するのが特徴です。
会社自体が消滅することで、会社が抱えていた債務も存在しなくなります。会社に残った資産からできるだけ債権者に配当されますが、不足分は回収できなくなるので、債権者にも大きな影響があります。
● 会社の資産は全てなくなる
法人破産によって、会社の資産は全てなくなります。破産をした会社の資産は全て換金されて、債権者に配当されるからです。個人が破産する場合、その後の生活に必要な最低限の資産が確保されますが、会社はその必要がないため、資産は全て処分されます。
● 従業員は解雇される
法人破産をすると、会社が雇用していた従業員は全員解雇されます。会社自体が消滅するので、もう従業員を雇えなくなるからです。 -
(3)法人破産の手続きの流れ
法人破産をするには裁判所に申し立てをします。法人破産は手続きに必要な書類や資料が大量にあり、手続き自体も複雑なので、弁護士に依頼して手続きをするのが一般的です。
弁護士に依頼すると弁護士費用がかかりますが、手続きを代行してくれるので裁判所に出向く必要がない、申立書などの書類の作成を任せられる、弁護士が受任通知を送ると債権者からの取り立てがなくなる、などのメリットがあります。
申し立てが受理されると、会社の資産や負債を管理する破産管財人が選任されます。管財人による財産の調査や換価、債権者集会などを経て、会社の債権者に配当が行われた後、会社の法人格が消滅して破産手続きは終了します。
なお、民事再生や会社更生という、会社を存続させながら債務を整理する方法もありますが、この方法は、破産手続きよりも債権者との難しい交渉をしなければなりません。
4、倒産後の経営者個人についての手続き
企業が破産手続をするにあたって、経営者が企業の債務を保証したり、個人名義で借金を負担したりしている場合は、経営者個人も自己破産をする必要性が高いです。そこで、経営者が自己破産する手続きの流れを解説します。
-
(1)経営者が自己破産するケース
会社と経営者は別人格なので、会社が倒産しても、経営者が当然に会社の債務を引き継ぐわけではありません。
もっとも、経営者が会社の債務の保証人になっている場合や、会社の運転資金のために個人名義でカードローンなどの借り入れをしている場合、会社が破産しても経営者には債務が残ってしまいます。
経営者自身で弁済できれば良いのですが、そもそも会社が倒産してしまう以上、経営者個人にも十分な資産がないのが一般的です。そのため、会社が破産手続をする場合、経営者も自己破産するケースが少なくありません。 -
(2)自己破産は手持ちの財産に影響する
個人が自己破産する場合、最低限の生活を維持するための自由財産と呼ばれる財産以外は、手放さなければなりません。自己破産しても手元に残しておける自由財産は、以下のとおりです。
- 99万円以下の現金
- 破産手続の開始後に新たに取得した財産
- 家財道具など、差し押さえが禁止されている財産
- 上記以外に裁判所が自由財産の拡張として認めた財産
自由財産に該当しない財産は手放すことになりますが、これには自宅も含まれる点に注意しましょう。なお、自己破産をしても家族が所有する財産に影響はありません。
-
(3)自己破産の手続きの流れ
自己破産をするには、まず裁判所に自己破産の申し立てをします。会社の破産手続と同様に、自己破産も手続きが複雑で、集めなければならない書類や資料なども多いため、基本的に弁護士に依頼して行いましょう。
裁判所が破産手続きの開始を決定すると手続きが始まりますが、破産管財人が選任されるかどうかで手続きが変わります。破産管財人が選任される管財事件の場合、管財人による調査や債権者集会などがあり、一般に手続きが複雑かつ長期化します。
破産管財人が選ばれない場合を同時廃止といい、手続きに必要な期間や費用は軽減されます。裁判所で裁判官と面接する場合もあれば、面接をせずに手続きが進行する場合もあります。
管財事件にせよ、同時廃止にせよ、最終的に裁判所が「免責が相当である」と判断すれば、税金などの一部の債務をのぞいて、自己破産によって経営者の債務が免責されます。
5、まとめ
当座預金の残高不足で手形が不渡りになると、1回目は不渡りの事実が通知されるだけですが、半年以内に2回目の不渡りを出すと、銀行取引停止処分を受けてしまいます。
銀行取引停止処分を受けると当座預金が利用できなくなるので、手形が振り出せなくなります。また、会社の信用が大きく低下して融資や取引が困難になる可能性があります。
手形の不渡りなどで倒産せざるを得ない場合、法人破産をすれば会社の債務は消滅しますが、経営者名義の債務を消滅させるには経営者自身も自己破産をする必要があります。
経営の立て直しはスピードとタイミングが重要です。手形の不渡りでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスにお早めにご相談ください。企業法務や債務整理に知見のある弁護士が、解決のためにお手伝いします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|