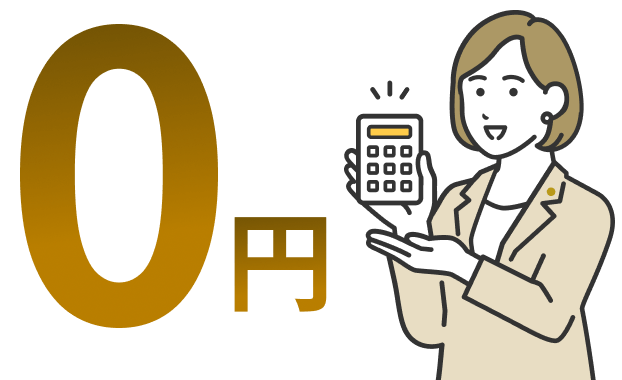事前に遺言書を作成するメリットは? その書き方と注意点を弁護士が解説
- 遺産を残す方
- 遺言書
- 水戸

TVや雑誌などを見ていると、「遺言書」という言葉を耳にする機会がよくあるのではないでしょうか。ひとごとのように聞こえるかもしれませんが、相続は誰にでも発生します。水戸で暮らしている方たちもひとごとではありません。
遺言書というのは、当人が亡くなった際に、誰にどのくらいの財産を分与するかという意思を生前に記した書類のことです。
相続が発生した際に、遺言書があるかどうかは大きな問題になります。遺言書があれば基本的にはその内容に従って相続財産を分けますが、そうでない場合は法定割合や相続人同士の話し合いによって財産を分けることになります。前者であれば被相続人の意思表示という明確な指針がありますが、後者の分け方はどうしてもトラブルに発展しがちです。
相続トラブルを避けるためにも、遺言書がどのようなものかを理解したうえで作成できるよう、弁護士が解説します。
1、遺言書の種類と特徴
遺言書にはさまざまな種類があります。まずはその特徴をしっかりと理解しましょう。
-
(1)自分で書く「自筆証書遺言」
自筆証書遺言は、被相続人が自ら紙に書く形の遺言書です。紙とペンさえあれば作成することができるため、非常にポピュラーな遺言書です。
しかし、自筆証書遺言は被相続人の意思のみで書かれているため、場合によっては内容があいまいとなってしまったり、記載内容が誤っていたりする可能性もあります。その場合は遺言書として法的な効力を発揮することができなくなってしまう点に注意が必要です。自筆証書遺言を書く際には、正しい書き方を事前に調べておく必要があります。また、内容を誰も証明できないことから、開封時には家庭裁判所による検認を受けなければなりません。 -
(2)公正証書として作成する「公正証書遺言」
公正証書遺言は、遺言を公正証書として作成する形になります。公正証書は、公証役場の公証人が法的な定めにのっとって作成するだけでなく、厳密に書類を用意することが求められることから、信頼性が高くなります。また、内容を証明された原本が公証役場に保存されるため、改ざんや紛失の心配がありません。開封時にも検認手続きは不要となります。
自筆証書遺言では不安だという場合は、公正証書遺言の作成を検討することをおすすめします。 -
(3)公証人に内容を知られない「秘密証書遺言」
秘密証書遺言も公正証書として作成する遺言書です。しかし、その内容を公証人に知られずに記載できるという特徴があります。内容を誰にも知られたくない場合には有効ですが、もし内容が誤っていたら法的な効力が無効となる可能性があります。公証役場は秘密証書遺言があることは証明してくれますが、公証役場で内容確認を受けることがないため、開封時には検認手続きが必要となります。実際にはあまり利用されることはないようです。
-
(4)緊急時のための「特別方式遺言書」
特別方式遺言書は、緊急的に遺言書を作成しなければならないときに用いられる手法です。たとえば、病気などで被相続人の死期が間近に迫っているときや、乗っている船や飛行機などが事故に巻き込まれてしまったときなどが挙げられます。
なお、特別方式の遺言書は、例外的に代筆が認められています。前述した自筆証書遺言及び秘密証書遺言の遺言書は、原則的に自筆であることが求められますが、特別方式の遺言書では、本人の口述を他人が代筆することができる場合があります。
2、有効な遺言書と無効になる遺言書
遺言書には民法にて正しい書き方が定められています。それにのっとって記載しないと、せっかく作成したとしても、法的に無効になってしまいます。また、内容によっても無効となってしまう場合があるでしょう。
以下、詳細に紹介していきます。
-
(1)法的に有効な遺言書
遺言書は財産の相続割合を定めるだけではなく、身分を確定したり、財産の管理人を指定したりするなどの役割を負わせることもできます。だからこそ、民法で正しい書き方が定められているのです。
●相続人の指定
どの相続人に、どのように財産を相続させるかを決めることができます。相続人を廃除することもできます。しかし、相続人を廃除するためには、相続人が被相続人に対して虐待や非行などの相続廃除原因が認められなければなりません。
なお、相続人の廃除は被相続人の生前でも行うことができます。その際は遺言書ではなく、家庭裁判所に請求して行うことになります。
●財産に関する指定
どのような財産を、どの相続人に相続させるのか、その割合はどうするのか、分割の方法もある程度指定することができます。しかし、相続人には遺留分という権利が認められています。遺留分というのは、各相続人の最低相続権のようなものであり、基本的には遺言書でもそれを侵害することはできないとされています。
各相続人の遺留分を無視した遺言書を作成すると、大きなトラブルの元になってしまいます。作成の際は注意する必要があるでしょう。
●身分の確定
遺言書によって、内縁の妻との間にできた子どもを認知し、相続人に加えることもできます。
●遺言執行者の指定
遺言書によって、遺言執行者を定めることもできます。適切な遺言執行者を立てておくことで、相続をスムーズに進めることが可能となります。
●祭祀(さいし)承継者の指定
遺言書によって、祭祀承継者の指定を行うことができます。祭祀承継者とは、一族の祭祀財産(系譜や墳墓など)を承継する方のことを指します。なお、祭祀承継者に選ばれた場合に継承する祭祀財産は、相続財産とはみなされないのが一般的です。 -
(2)無効になってしまう遺言
次に、法的な効力を失ってしまう遺言について知っておきましょう。
●自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言で無効になるケースとしては、下記のようなものが挙げられます。
- 被相続人の自筆ではない遺言書(パソコンなども認められません)
- レコーダーなど音声として残された遺言書
- 押印や日付、署名のない遺言書
- 相続財産の内容があいまいな遺言書
- 複数人によって書かれた遺言書
自筆証書遺言は、被相続人が自分で「自筆」するのが大原則です。特別方式とは異なり、口述による代筆も認められていないので注意しましょう。ただし、平成30年に行われた法改正により、翌7月以降に作成された遺言書であれば、財産目録のみパソコンなどでの作成が認められることになっています。詳細は弁護士に確認することをおすすめします。
●公正証書遺言の場合
公正証書遺言で無効となるケースには、下記のようなものが挙げられます。
- 公証人が不在時に作成された遺言書
- 証人に不備のある遺言書
- 公証人に口授ではない方法で伝えられた遺言書
公正証書遺言は公証人が法の定めにのっとって手続きを行うため、自筆証書遺言に比べると無効となるケースは少ない傾向にあります。
●特別方式遺言書の場合
特別方式は、証人に対する規定が特に厳密に規定されています。
たとえば、一般的な状況で非相続人の危篤時に特別に作成される遺言書には、3名以上の証人の立ち会いが必要とされています。また、船や飛行機に乗っており死期が間近に迫っているような場合でも2名以上の証人が必要と規定されています。これらに反した場合は無効となる可能性があります。また、特別方式によって遺言書を作成したのち、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになってから6ヶ月生存している場合は、特別方式遺言書の内容は法的な効力を失います(民法第983条)。
そのほか、「家族仲良く」などあなたの感情的な望みを書き残すことはできますが、法的な効力を持たせることはできません。しかし、遺族に対してあなたの思いが伝われば、争いになる可能性を少しでも低くすることができるでしょう。
3、遺言書を作成するメリット
最後に遺言を作成するメリットについて考えてみましょう。
-
(1)財産の分配について指定できる
遺言を作成することで、ある程度自分で思うように財産を分配することができます。
しかし、いくら被相続人といえども遺留分を侵害することは原則的にできません。分割の割合を考える際は注意しましょう。 -
(2)相続が「争続」になるのを防ぐ
遺言書がある場合は、ない場合と比べると相続がスムーズに進む傾向にあります。法的にも相続割合は定まっていますが、被相続人の意思に基づいて分配された方が相続人も納得できる側面があるでしょう。
-
(3)相続権がない方にも相続させることができる
遺言書を残すことで、法定相続人以外にも財産を分けることができます。
たとえば、生前お世話になった方にある程度の財産を相続させたいというときには、遺言書の作成を検討することをおすすめします。
4、まとめ
遺言書を作成することで、ある程度自分の意志に沿った財産の相続が可能となり、後々のトラブルを防ぐことができます。しかし、遺言書はしっかりと規定にのっとって書かなければ効力を発揮しません。
また、明らかに相続人が不服を抱くような内容にせず、なるべく円満に、残された相続人がもめないような分配を行いましょう。
遺言書の書き方に不安がある方は、弁護士のサポートを受けると安心です。遺言書作成に対応した実績が豊富な、ベリーベスト法律事務所・水戸オフィスへお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています